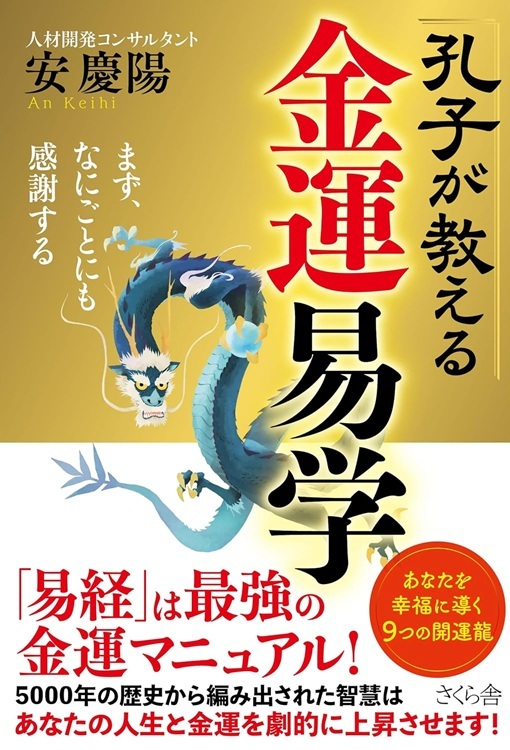本記事は、安 慶陽氏の著書『孔子が教える金運易学』(さくら舎)の中から一部を抜粋・編集しています。

お金は御足様?
日本語で、お金のことを「御足(おあし)」と
呼ぶことがあります。
これには諸説ありますが、
1つは江戸時代につくられた代表的な銭貨
「寛永通宝(かんえいつうほう)」の
裏に「足」という文字が刻印されていたため
といわれています。
ちなみにこの銀貨の裏にある「足」という文字は、
寛保年間(1741~1744年)に
足尾銅山で産出された銅を
原料としてつくられた証だそうです。
また、一文銭の裏側にあることから、
「足字銭(あしじせん)」とも呼ばれています。
さらに、
「金は天下の回りもの」
ということわざがあるように、
「お金というものはまるで
足が生えているかのように、
世の中を行ったり来たりするものだから」
という説もあります。
ということは、
昔の人たちも「お金というものは
自分のほうにくることもあるけれど、
去っていくこともある」と感じていたのでしょう。
お金に対する感覚というのは、
昔も今もそう変わらないということ
なのかもしれませんね。
自分のほうにお金がたくさんやってきたら、
どんな人でも嬉しいはずです。
けれど、
お金が去っていくときは、
不安や焦りや罪悪感など、
なぜかネガティブな感覚に
陥ることが多くありませんか?
もしかすると、
そういうあなたの意識の状態が、
ますますお金を遠ざけてしまっているかもしれません。
「欲しい」「もっと欲しい」と思えば思うほど、
お金は手元にやってこなくなります。
男性でも女性でも、
好きな人をしつこく追いかけると、
逃げられてしまうでしょう。
お金も同じです。
ちょっとここはいやだなと思うところからは、
さっさと逃げていくのです。
やはり、お金には足がついているようです。
けれども逆に追わずにいると、
お金は戻ってきます。嬉しいことに、
お友達も連れて一緒に戻ってきてくれます。
ではどうしたら、
お金は戻ってきてくれるのでしょうか。
そのために必要な考え方を説いているのが、
「易(=易経)」です。
儒教の経典として知られており、
自然の摂理や森羅万象における
原理原則が書かれています。
孔子は、
この易を非常に熱心に読んでいたといわれます。
『論語』の中に易に関する記述があることから、
孔子の思想にも影響を与えたことも考えられます。
現代においても、
多くのビジネスパーソンが
その考え方を取り入れています。
易経では、
お金は自然界において「兌(だ)(=沢)」を
象徴するものとされます。
「兌」の文字の起源を見ると、
「八」「口」「人」で成り立っています。
これは人が口を開けて笑っている様子、
喜んでいるさまを表します。
そこから、
お金は喜びのエネルギーであると
考えることができます。
喜びのエネルギーを集めるには、
相手を喜ばせるのがもっとも近道です。
相手を喜ばせば喜ばすほど、
お金はあなたの周りに寄ってきます。
ここではまず、
お金に対する向き合い方に話を戻しましょう。
私が易経の講義で
お金や豊かさについて説明する際、
よく「たらいの法則」についてお話をします。
たらいは、
現代ではまず見ることがありませんが、
同じことが湯船に浸かって
お湯をかき混ぜるときに起きます。
お湯を自分のほうに寄せようとすればするほど、
お湯は向こうに流れていきます。
ところが、
向こうに押すと自分のほうに戻ってきます。
お金や豊かさの流れもこれと同じということです。
自分のほうに引き寄せようとするほど、
逃げていきます。
けれども、
どうしたら相手が喜んでくれるかを常に考え、
相手に与えようとするほど、
自分のほうに巡ってくるのです。
お金は足がついている「御足様」ですから、
お金が自分の足でこちらに
歩み寄ってくれる人になりましょう。
そのやり方を本気で実践していけば、
誰もがお金に好かれる人になることができます。
なぜお金はあなたから
去っていくのか?
「お金が欲しい」「もっと儲けたい」
「またお金がなくなった」などの言葉は、
「お金がない」状態を指しています。
これは「お金がない」と言っているのと同じです。
お金がある人は、
このような言葉は発しません。
さらに、
あなたが「お金がない」と言うとき、
その言葉を常に聞いている人がいます。
それは誰ですか? …… あなた自身です。
口癖のようにお金がないと言っていると、
それを聞き続けているあなたの脳に刷り込まれます。
すると、
「お金がない」という状況を作るべく、
無意識のうちにお金が離れていく
ような選択をしてしまうのです。
そしてもう1つお伝えしたいのが、
「バランス」です。
易経でも、古代中国で確立された「陰陽」
の考え方がベースにあります。
古代から森羅万象、
宇宙のありとあらゆる物事は「陰」と「陽」
という2つのカテゴリーに
分類されるというものです。
たとえば、
陰=月、夜、秋冬、水、女性など。
質的には静、重、柔、冷、暗などがあります。
一方、陽=太陽、昼、春夏、火、男性など。
質的には動、軽、剛、熱、明などがあります。
1つの物事、事象に対して、
対立するものがあってはじめて
お互いが存在すると考えます。
そしてこれらは、
常に変化を繰り返します。
陰である月が昇るとき、
陽である太陽は西に沈みます。
月が天高く昇り、姿を消す頃、
太陽が東の空から昇ってきます。
これを「陰極まれば陽になり、
陽極まれば陰になる」と、
中国の人は捉えました。
ずっと陰のまま、
陽のままではいられません。
陰も行き着くところまで行けば、
陽に転じます。
逆も同様です。
変化を繰り返しながら、
バランスを保っているのです。
これを、お金の損得に置き換えて考えてみましょう。
もしある人が大儲けをしてお金が集中し、
自分のところに貯め込もうとすると、
ほかの人のところにお金が回らなくなります。
すると、経済もうまく回りません。
儲けたお金を使ったり、
与えたりすることでお金が回り、
経済が回ります。
そして社会もうまく動いていくのです。
このように陰陽のバランスは、
どちらかに極端に傾くとバランスを崩します。
バランスを保つために大切なのが、
「中庸」です。
どうすれば儲けられるかを考えつつ、
どうすれば相手も喜んでくれるかに思いを馳せ、
陰陽のバランスを取りながら、
その間にできる道(中庸)を進んでいくということです。
ともすれば、
私たちは「いかに自分が得をするか」
「損をせずに済むか」を考えがちです。
もちろん、
ビジネスには必要な観点なので、
こうした思いを持っていてもいいのです。
ただ、それも度が過ぎると、
仕事やお金はうまく巡っていきません。
もし今、自分の元からお金が
去っていく一方だと感じているなら、
陰陽のバランスが崩れていると考えられるのです。
裏を返せば、
このバランスを整えていきさえすれば、
今までとは違う流れを呼び込めるということです。